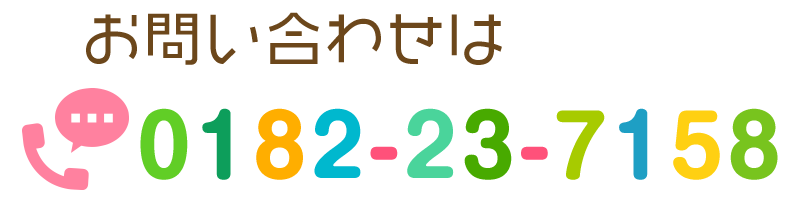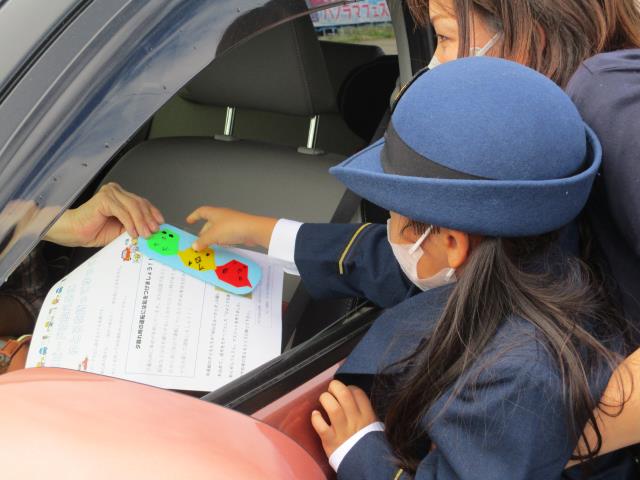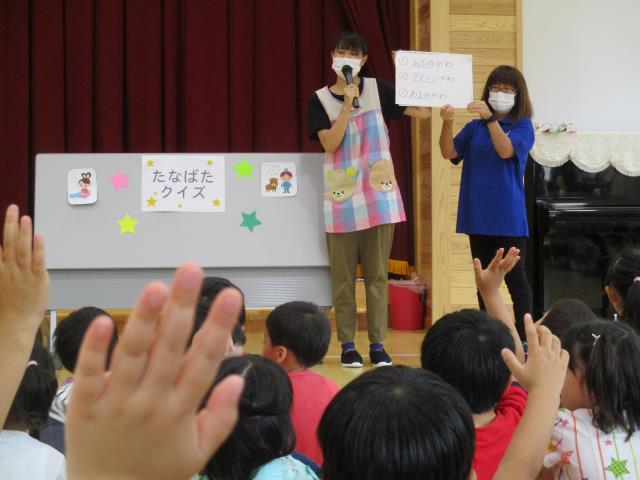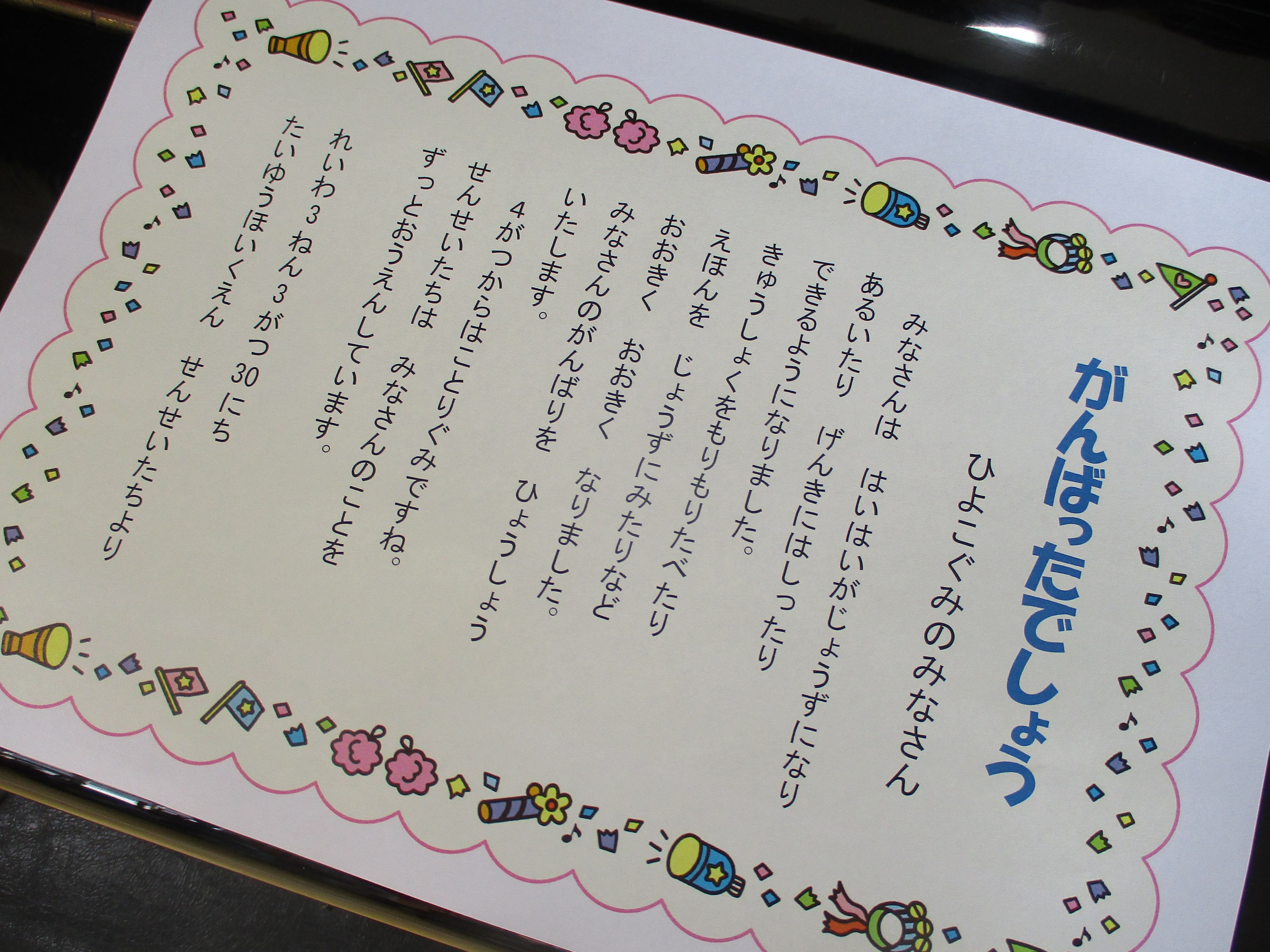「メリークリスマス!」
12月23日、たいゆう保育園ではクリスマス会が行われました。
この日を待ちに待った子どもたちです、その理由は・・・
サンタさんに会えるから?
プレゼントをもらえるから?
そんな野暮な質問はともかく、子どもたちの期待いっぱいの表情は、クリスマス寒波をはねのけます。
クリスマス会独特の雰囲気の中、子どもたちはサンタさんの登場に「わぁ~!」の一言。
子どもたちが用意していた質問の答えを聞きながら、自分たちの想像と答え合わせです。
サンタさんには練習してきた踊りをみてもらい、そしてサンタさんからは、もれなく子どもたち全員にプレゼントが手渡されました。
サンタさんが去った後は、恒例のクリスマスコンサート。
今回は先生たちのバンド演奏にぞう組(年長組)の子どもたちのダンスが加わり、さらに、ギターを手作りをした子どもたち2人が演奏に加わりセッション!
新しい形のクリスマスコンサートとなりました。
クリスマス献立の給食も大人気。
「好きな物だらけだった!」と、声を弾ませた女の子の姿も見られました。
今年も大盛り上がりのクリスマス会となりました!